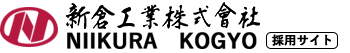生成AIを使った開発、特許とれるか議論 特許庁
特許庁は、特許法の見直しに向けて有識者会議を開いた。
生成AI(人工知能)を使って開発された発明品について人が特許権をとれるかどうかの議論を始めた。
現行では抽象的なアイデアを出すだけでは開発者として認められないケースが多い。
人が課題設定やアイデアを出して、生成AIが化学式などの組み合わせを創作した場合、人を開発者にできるかが明確になっていなかった。
特許法の解釈の変更も含め、対応を検討する。
有識者からは「AI技術が日進月歩で発展しているなか、数十年先を見込んだ議論が必要だ」といった指摘があった。
特許庁は2026年にも特許法の改正を目指している。
開発予定のない事業者や個人が生成AIを使って新製品の開発を妨げた場合でも正規の発明者を保護する仕組みづくりも検討する。
特許権の登録には新規性の条件があり、出願前に国内外で公開されると権利が得られない恐れがある。
海外サーバーを利用した国内サービスも条件を満たせば特許の保護対象にする方向で議論する。
アッシュ研修で生成AIの有能さを学びましたが、私の業務や生活に人工知能を取り入れてはおりません。
まだまだ自力で脳みそフル回転です。
生成AIの進化の速度はこの1年で飛躍的に加速しています。
もともと生成AIは、ディープラーニングや画像認識モデルなど新しい技術の出現により進化が進んできました。
1950年代の概念提唱からの発展を経て、現代において大きな進化を遂げています。
記事の中にもあった様に「数十年先を見込んだ議論」を始めていますが、もしかしたら人工知能の進化はその議論の斜め上を行くかも、と期待してしまいます。
特許については知識と接点がありませんが、生成AIによる害まであるとは驚きでした。
開発者の保護と自由な競争による技術進歩の両立は容易ではないと思いますが、良い塩梅にしてもらえることでしょう。
それぞれの部署や業務内容で生成AIとの付き合い方は違ってくるとは思いますが、時代に取り残されない為にも少しずつでも取り入れて行きたいです。