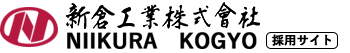手先が不器用になる子どもたち、「驚くべき異変」を専門家が危惧
現代の子供たちは、重要な「微細運動能力」を失いつつある。
微細運動とは、靴ひもを結ぶ、ペンで字を書く、物を積み上げるといったときに必要な、細かく正確な動きのこと。スマートフォンやタブレット端末、電子書籍、テレビなどの画面を見ている時間であるスクリーンタイム、生活習慣の変化、子供時代の体験の変化といった要因が複雑に絡みあった結果だと専門家は指摘する。
スクリーンタイムは、子供が何かを作ったり組み立てたり、絵を描いたりする時間を削る。
そうした端末を使った算数の学習やデジタルアートの作成は、教育効果はあるが、書く、切る、色を塗るといった動作に伴う細かな運動能力を育てることはできない。スクリーンタイムが長いほど微細運動能力の発達の遅れにつながることが、研究でわかっている。
子育てに便利なものが登場したことも、運動能力の発達に影響を及ぼしていると専門家は言う。
時間の節約になるゴムのズボンは、子供がファスナーの開け閉めやボタンの留め外しを練習する機会を奪う。
個包装のおやつでは、食器の扱いに慣れるチャンスは得られない。
子供自身も、根気や正確さを必要とするパズルや積み木より、簡単にくっつくマグネット式タイルを好むなど、
選ぶおもちゃに変化が出てきているという。
子供たちに広がる読書離れも、単純作業に対する集中力の低下を招き、微細運動能力の低下の大きな要因のひとつになっているという。
この記事では子供に焦点が当てられていましたが、同じことが大人にもあてはまるように感じられぎくりとしました。
便利だ、時短だ、といって様々な手間をカットした結果、別のところで大切なものをなくしてはいないか。
スクリーンタイムが長くなれば不利益が多くなることは大人だって同じはずなのに、子供に「スマホは1日何時間まで」と約束させる親の何割が、自分にも同じようにスマホ時間の制限をかけているだろうか、と寝る直前までついつい画面を見てしまう自分を反省しました。
仕事においても、業務の効率化のためにお客様からの信頼を損なうことがないよう、大切なことの優先事項を間違えないよう、意識して取り組んでいこうと感じた記事でした。