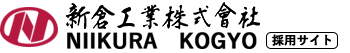令和の米騒動、責任は政治にある 小泉進次郎農相
令和の米騒動で農政の綻びが露呈している。
米価の空前の高騰は政府備蓄米を放出しても収まらないまま。
問題は流通の目詰まりといった足元の話にとどまらない。
価格の低下を防ぐ生産調整を続けてきた結果、担い手不足が進んで産業としての持続可能性さえ揺らいでいる。小泉農相は流通の見える化を進めるため、競争入札ではなく随意契約を採用し、集荷業者や卸を排除して小売店に直接接触する方針を取った。
さらに店頭価格の目安にも言及し、備蓄米の放出や情報発信を見直すことでコメ価格を抑制しようとした。
また、従来の方法では迅速な供給ができないと認識し、大胆な変革を決意した結果、民間企業の迅速な対応に驚かされた、民間の競争の力はすごいと言う。
2015年から2年間、自民党農林部会長を務めた。部会長は率直に言うと中間管理職。政府と党内の声をひとつの方向にする役目を担う。現在の農林水産省の中には当時の小泉農相を支えてくれたメンバーもいる。全省を挙げてコメの改革に取り組むため渡辺毅次官にチームのトップに就いてもらった。
部会長経験がなければ、今回の随意契約による備蓄米放出と早期の店頭販売は実現できなかったと語る。
これまでの日本はコメ余りを心配してきた歴史や経緯があるが、状況は大きく変わった
生産を増やして余ったら『国が(面倒を)』というのは間違いだ。
需要に応じた生産が大事。万一の時に国が買い上げる時代に戻るわけにはいかない。よく『余ったら輸出しろ』と言う人がいる。余ったから買ってくれなんて、ビジネスはそんな甘い世界ではない。ちゃんと(日本産が売れる)マーケットをつくらないといけない。戦略を持った政策を考えたいと語る。
「コメから始まるのではないか。コメの分野の改革をしっかりと進めることが、結果として農政全体の改革につながる。だからコメに集中して取り組むことが必要だ」
この記事から日本の農業政策の問題がよくわかりましたし、農協中心の体制からの脱却を目指している点は、今後の農業において重要だと思いました。
この記事の小泉農相の改革を進めるときのスピード感と、今後を見据える力は目を見張るものがあり私は今月で入社1年となりますが、手本としたい内容でした。
また、一つ一つの事を積み上げ、ただ経験を増やすのではなく、経験を信頼や学びに変えていけるように日々精進したいと思えた記事でもありました。