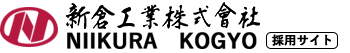トランプVS.大学 研究ピンチ
米国のトランプ政権による突然の支援削減で、米国の大学の研究が危機に瀕しています。
医療や人工知能(AI)などの研究が中止や縮小を迫られ、代わりとなる資金のめども立っていない状態になっています。
3月にトランプ政権がコロンビア大学への助成金4億ドルの差し止めを決めたことにより、共同で研究を進めていた他の大学にもその影響が広がっています。
ハーバード大学医学部主導の研究チームにはコロンビア大学の研究者が関わり、助成金もコロンビア大学を経由して提供されていたことで、現在は嘆願と代わりとなる資金集めに奔走しているそうです。
この研究チームは、全米各地に住む1700人の糖尿病患者を対象に、1990年代から生活習慣の影響を定点観察するプロジェクトを進めており、直近では糖尿病と認知症の関連について米連邦政府から5年間の助成を受けた研究を進めていました。
コロラド大学においても、子供のSNS利用が広がる中で、AIが作るコンテンツの仕組みや問題への理解を深める方法を研究するプロジェクトが、助成金打ち切りを通告されたとのことです。
助成金打ち切りの影響は大学のみにとどまらず、米科学財団の予算を25年度比56%、医療研究を支援する国立衛生研究所の研究予算を25年度比37%それぞれ削減する案が示されています。
業界団体の米医療研究連合はこれらの予算削減案が医療研究に「壊滅的な影響を与える」と警告しています。
米国には様々な分野で最先端を行く先駆者的なイメージをもっていましたが、長期的な視点よりも今を優先する国になってしまったかとこの記事を読み、驚きました。
しかし、自分自身は「長期的な視点」を持てているのかと言われれば、そうではないなと感じております。
例えば、整備品の整備対応中に別の整備品が短納期で返却された場合、優先順位に戸惑う自分は想像に難くはありません。整備途中だからと言って頑なに短納期の製品を後回しにしてしまっては、納期を守ることはできず、お客様に不信感を抱かせる原因になります。
整備品を担当させていただくお客様と長期的に良好な関係でいるためには、納期という約束事を守るために、時には状況に応じた柔軟な対応も必要であるととらえています。
現在の米国の姿勢は「いつ開花するかわからない研究にお金を費やすよりも、今は出費を抑えることが優先」と言っているかのように感じました。
研究に携わる人たちはよりよい未来を実現させるために長期的な視野を持って取り組んでいると私は考えます。
その道を断ち切ってしまうことは、米国の進歩を止めてしまうことになるのではないでしょうか。
米国政府による資金提供の打ち切りがどのような結末を迎えるのかは誰にもわかりませんが、私自身はこの記事を反面教師にし、一度担当した整備品とは長期的な関係を結ぶつもりで今後も業務に取り組んで行きます。