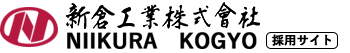データで読む地域再生 宿場町の「お茶請け食文化」
東海4県で文化庁が認定する「100年フード」の制度を活用し、地域の食文化を地域振興に活かそうとする動きが広がっており、地域の知名度向上や観光客の呼び込みを狙う自治体や商工会議所が増えています。
「100年フード」とは地域で愛される食文化を認定する制度で、認定団体はロゴマークの使用などができるようになります。
東海4県には100年フードとして認定された食文化が多く、愛知県は12件で全国3位、三重県が9件で8位、静岡県・岐阜県は6件で21位となっております。
100年フードの制度を活用した各県の取り組みは様々で、例えば愛知県瀬戸市の100年フード「瀬戸焼そば」は小学校の調理実習でも作られ、食文化の継承に向けた取り組みが進められています。
愛知県長久手市のジブリパークの開園に伴い、観光客の宿泊が増えていることから、瀬戸焼そばが食べられる飲食店をまとめたパンフレットのホテルなどへの配布で、さらに認知度の向上を目指しています。
静岡県では2022年、東海道の宿場町が多い大井川流域で地域のお茶と共に旅人をもてなしていた食事「大井川のお茶請け食文化」が100年フードとして認定を受けております。その代表格の一つが「瀬戸の染飯(そめいい)」で、これを活用した弁当販売を地域で進めています。
三重県でも伊勢うどんを表紙にした学習帳を伊勢市内の小学生に配布し、岐阜では朴葉(ほおば)を使った食文化が認定を受けており、朴葉は自然に還る素材であることから、現代のSDGsにもつながる考えを受け継ごうとする動きが広がっています。
この「100年フード」の制度はこの記事を読んで初めて知りましたが、食文化を地域活性につなげるための有意義な制度だと感じました。
「100年フード」のことを知らずに地域のイベントなどで弁当を手に取った人には、その日の出来事と共に地元で愛される料理を楽しむことができ、その時の印象はきっと後にも残るのではないかと思います。
また、この制度や取り組みの優れている点は、地域の伝統や技術の継承を確実に行う仕組みづくりをせざるを得ないところではないでしょうか。
同時に、地域の人々の協力や技術を継承する意欲がなければ達成できないものでもあるかと思います。
自分の業務においても同様で、新倉工業製品の品質は、技術継承によって保たれてきたものと考えております。会社の看板に傷をつけないことはもちろんですが、アフターメンテナンスに携わる者としてお客様に「あなたに預ければ大丈夫だ」と思っていただけるよう、今後も技術の研鑽、向上に努めてまいります。
又、猛暑が多発し熱中症になる人も増えてきているので、食べ物で栄養を補給したり、新倉製のミストシャワーを使って冷却するのも良いことだと思いました。