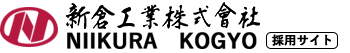日本製の艦艇を初輸出、ドイツに競り勝つ 官民一体で「弱点」克服
日本製の艦艇がオーストラリア海軍の次期フリゲート艦に採用される方向になった。
総額1兆円規模となる初の艦艇輸出に道筋をつけたのは、過去の教訓を生かして相手国のニーズに応えながら売り込みをかける戦略だった。
輸出によって国内防衛産業の育成に弾みがつけば日本の防衛力強化につながる。
攻撃能力を持つ自衛隊の主力装備品が外国に採用されるのは初めてだ。
豪政府はフリゲート艦選定の最終段階で日本製の「もがみ」型護衛艦改良型とドイツ製に絞り込んでいた。
競り勝った要因は豪州側のニーズに配慮したことだ。豪州が使う米製戦術ミサイル「トマホーク」などを搭載できるよう艦艇を共同開発する案を示した。
ドイツの提案は欧州製の防空ミサイルを使用するものだった。
コストにも気を配った。
「もがみ」型の強みは運航に必要な人員数にある。ドイツ製の120人に対し、日本製は90人で済む点を強調した。
防衛装備庁と三菱重工業の幹部は「乗組員を減らせるので全体でみれば安くできる」とプレゼンした。
船体寿命や年間の稼働日数も日本製がドイツ製を上回った。
日本は米国にも後押しを働きかけた。中谷元防衛相は3月のヘグセス米国防長官との会談で、豪州への艦艇輸出に支援を要請した。輸出する艦艇に米国製のミサイルを搭載するため、米国にも利益があると訴えた。
官民一体でセールスをかけた背景には10年代の苦い経験があった。
豪州から海上自衛隊の「そうりゅう」型潜水艦を輸出してほしいとの打診があったにもかかわらず、最終的に選ばれたのはフランス製だった。
輸出経験がなかったため当初、豪州側の関心に即座に対応できなかったのが響いたというのが日本政府の敗因分析だ。この教訓を踏まえ、今回は豪側からの関心が表明された直後から官民で売り込みをかけた。海自訓練の機会に豪州側に艦艇の実物を見せた。
製造する三菱重工は現地に事務所を立ち上げた。
日豪政府は26年初めに最終契約する。
11隻の総額はおよそ1兆円で、日本の防衛産業にとって前例のない大規模な輸出の経験となる。
この記事を読んで、日本の艦艇がオーストラリア海軍に採用されることが決まったのはすごく嬉しいニュースだと感じ、また日本の技術が世界で認められ、オーストラリアのニーズに合わせた提案やコストの面での優位性が評価されたのも、企業がしっかり戦略を考えているからだと思いました。
過去の失敗から学んで、官民一体で迅速に対応した点も素晴らしいと思いました。
現在、週一日製造部に研修に行き、製造部の皆様に製品を作るポイントや製品の構造等を聞いています。また、勉強会を週一回開催して頂いております。
自社の製品の事をもっと知り、他社製品と比べたときに弊社の製品がいかに優れているのかを、説明できるようになりたいと思いました。